コンテンポラリーダンスって何!という方に、簡単に、わかりやすく説明します!
コンテンポラリーダンスとは、決まった振り付けやルールに縛られない踊りのこと。
要するに、固定の基準を持たない“自由度の高いダンス”といえますね。
というわけで、この記事ではコンテンポラリーダンスについて、サクッと知りたい方もしっかり知りたい方も、どちらにも満足いただけるように2つの構成に分けて作っています。
ぜひ最後までご覧ください!
【最初に要約】コンテンポラリーダンスとは?
コンテンポラリーダンスは、決まった型やルールに縛られず、自由な身体表現を重んじる踊り。
ヒップホップやジャズなどが物語性や感動を伝えやすいのに対し、「分かりにくい」と言われがち。
ただ、その予測不能な展開や多様性こそが魅力。
起源はヨーロッパ。
1960年代のモダンダンスへの新潮流から派生し、1980年代の「ヌーヴェルダンス(新舞踊)」を経て「コンテンポラリーダンス」と呼ばれるようになりました。
1990年代には音響・照明・美術・ITなどを舞台に複合導入し、ストリートや舞踏の要素も融合して発展していきます。
「意味不明」よく言われますが、型がなく日常離れした動きや道具の使用(巨大な布、紙を破く動きなど)があるため。
理解より「感じる」ダンスと言えばなんとなくわかるでしょうか。
地域によっても異なる部分があり、
ヨーロッパでは公立劇場系の集団的芸術と、少人数・多媒体の実験的芸術に分けられます。
ラテンアメリカはサンバに代表される色彩豊かなリズム文化が源流で、イスラエルはバットシェバ舞踊団のGAGAメソッドが知られる。
日本では認知度こそ低いものの、日本舞踊が取り入れられているため、関わりは深い。
また、実は有名楽曲に採用されていたりするので目にしている人は多い。
オーストラリアは多文化と新技術をテーマに、環境・障害・人種など現実課題を扱い、バーチャル空間の演出も発達。
代表例として、土屋太鳳×Sia「Alive」、米津玄師「Loser」、森山未來「CeBIT」、欅坂46「不協和音」など。
世界共通の厳密な定義はなく、文化や時代に応じて更新され続ける“何でもあり”のダンスであり、背景やテーマを「感じる」ことがほんとに大事。
コンテンポラリーダンスについて詳しく紹介!
既存のヒップホップやジャズ、ミュージカルのダンスは、物語性や感動が伝わりやすく観客に理解されやすい一方、コンテンポラリーダンスは抽象的で難解と感じる人も少なくありません。
ただし、自由度が高く多様で、時代とともに姿を変え続けるため、予測のつかない面白さが魅力でもあります。
コンテンポラリーダンスのルーツはヨーロッパにあるといわれます。
西洋の要素に加え、アフリカンダンスや日本舞踊の要素を取り込むこともあり、非常に多彩です。
また、その時代の先端を切り開く作品や技法を指す言葉としても使われます。
その時々に生まれた新しい踊りをまとめて「コンテンポラリー」と呼んできた背景があり、たとえば1960年代に広まったストリートダンスや、シルク・ドゥ・ソレイユの現代サーカスなども同列に語られてきました。そもそも“コンテンポラリー”は「現代的」という意味を含むため、定義は曖昧で、すべてのダンスに機械的に当てはまる概念ではありません。
このような事情から、ダンスだけでなく用語そのものが「わかりづらい」と感じられることもあります。実際には、名乗った者勝ちのようにラベリングされてしまう側面も否めません。
近年は、伝統的なバレエや演劇の分野でもコンテンポラリーの手法が取り入れられ、既存のルールを解体するような作品が多く生まれています。既成概念を更新し、革新的なダンスへと進化していく可能性があります。
コンテンポラリーダンスの歴史
コンテンポラリーダンスの起点は、1960年代にモダンダンスへ対抗・補完する形で始まった新しい運動です。そこから技法や様式が派生し、後のヌーヴェルダンスを経て、現在呼ばれるコンテンポラリーダンスへと接続します。語源はフランス語の「danse contemporaine(ダンス・コンテンポランヌ)」です。
1970年代のフランスでは、文化の地方分散(デサントラリザシオン)が推進され、芸術分野に大規模な予算が投じられました。身体芸術の領域では、現代舞踊団や現代バレエ団の設立が進み、これがコンテンポラリー誕生の土壌になります。
新設の現代バレエ団では、古典バレエに新要素を加えたり、あえて“反バレエ”的な表現が試みられました。フランスを発信源として、ヨーロッパ全域、さらにアジアや中東へと広がり、各地の文化を取り込みつつ“革新のダンス”として発展していきます。
もともとコンテンポラリーはフランス語の「ヌーヴェルダンス(新舞踊)」とも呼ばれ、1980年代のフランスで流行しました。ドイツのダンスシアターやアメリカのポストモダンダンス、日本舞踊などを取り込み、表現の幅が一気に広がり、身体の限界に挑むような振付も次々と生まれます。
ヌーヴェルダンスは、クラシックバレエからの脱却をめざす試みとして拡張しました。1990年代には新たな技法を求める動きが強まり、音響・照明・美術・ITを舞台と複合させる例が増加。ストリートダンスや日本舞踏(舞踏)などの要素も取り入れられ、呼称はヌーヴェルダンスからコンテンポラリーダンスへと変わっていきます。
コンテンポラリーダンスが「わかりにくい」と言われるわけ
自由な身体表現であるがゆえに、はっきりした型や特徴が見えづらく、「何を表しているのか分からない」という声が出やすいジャンルです。「理解する」というより「感じる」芸術だとする見方もあります。
多くのダンスがストーリー性や明快さを重視するのに対し、コンテンポラリーはその逆を突く場合もあります。日常にはない奇妙な動きや人間離れした表現が含まれることも珍しくありません。
複数人で絡み合う、道具を用いるといった演出も特徴的です。大きな布と一体化して動いたり、紙を破る所作が振付に組み込まれる場面もあります。
解釈が一つに定まらない分、ダンサーの世界観が濃く立ち上がる点が魅力とも言えます。意味が完璧に分からなくても、観客が何かを“受け取る”ことで成立する、そんなタイプの舞台芸術です。
世界の地域別にみるコンテンポラリーダンス
コンテンポラリーはフランスから世界に広まり、各国の文化的背景によって独自の表現が育ちました。共通の基準がないため、受け取り方も多様です。
一方で、マスメディアでは依然として従来型のエンタメが主流で、コンテンポラリーは相対的に露出が少ないのが現状。認知が広がらなければ、立ち位置も上がりにくいままです。
この状況を変えるため、支援策を強化する国も増えています。ここでは地域ごとの特徴を概観します。
- ヨーロッパ
- ラテンアメリカ
- イスラエル
- 日本
- オーストラリア
ヨーロッパ
ヨーロッパでは、大きく「集団的芸術」と「実験的芸術」の二つの潮流があります。
前者は、公立劇場やバレエ団を母体に、従来のダンスを踏まえつつ躍動感あふれる表現で観客を魅了するもの。伝統的な劇場での上演が中心で、オランダ、イギリス、ギリシャ、さらにポーランド・エストニア・ブルガリアなど東欧で盛んです。各国の文化的土壌が反映されていると考えられます。
後者は、ファッションや映像など多媒体と積極的に交わり、観客とユーモアを共有する志向が強い系譜です。高度な訓練を必須としない作品も多く、少人数の創作が中心。小劇場や屋外など場所を問わず展開されるのが特徴で、フランス、ポルトガル、オーストリア、ドイツ、ベルギーといった西欧で顕著です。
ラテンアメリカ
ラテンアメリカ、とりわけブラジルではサンバがよく知られています。ヨーロッパのモノトーンとは対照的に、色彩豊かで華やかな踊りです。
もともとはアフリカ系住民が独特のリズムで集団で踊ったのが起源で、アフリカの伝統音楽バトゥーキに由来します。バトゥーキはカーボ・ヴェルデ発祥で、音楽と踊りが結びついた文化が根付いています。第二次世界大戦後はアメリカ音楽の影響を受け、白人向けサンバとして生まれたボサノヴァが人気を博しました。
サンバは打楽器に合わせ、体を揺らしながら前後に激しくステップを踏むのが特徴。ブラジルの歴史と文化が融合した、広い意味での“コンテンポラリーな”表現と見なすことができます。
イスラエル
中東のイスラエルでは、実はコンテンポラリーが盛んです。ダンスの中心地バットシェバには世界中からダンサーや演出家が集まり、表現を競い合いながら交流しています。
一方で、イランのように宗教的事情からダンスが認められない国もあり、中東全体としては一様ではありません。日本では森山未來さんが文化交流使として派遣されたことで、イスラエルのコンテンポラリーが一気に注目されました。
イスラエルのダンスは固有文化とヨーロッパの影響を掛け合わせて独自のスタイルを生み出しています。代表例の「バットシェバ舞踊団」では、GAGA(ガガ)と呼ばれるメソッドが知られています。未経験者でも感覚と想像力を引き出し、普段眠っている身体の部分を目覚めさせることで、可能性を広げていくアプローチです。
日本
日本では、コンテンポラリーは既存ジャンルに当てはまらないものとして受け止められがちです。ヨーロッパや南米に比べ認知度が低い点も要因でしょう。
「これまでと違う全く新しい踊り」がコンテンポラリーだと理解され、未開拓の領域として扱われる傾向があります。教育機関で学ぶ機会が乏しいことも課題です。
日本のコンテンポラリーの源流には日本舞踊が挙げられ、フランスのヌーヴェルダンスにも影響を与えました。時代が大きく変化している現在、従来のコンテンポラリーもさらに更新されていくはずです。
オーストラリア
オーストラリアのコンテンポラリーは近代的で、多文化や新技術の可能性を深掘りします。環境問題、障害、メディア操作、人種差別といった現実的テーマが主軸です。
ヒップホップやブレイクの動きを取り込みながら、舞台にテクノロジーを導入してバーチャル空間を立ち上げるなど、最先端技術とダンスを融合させた表現が発達しています。
オーストラリア独特の皮肉やユーモアをダンスに落とし込む点も興味深く、他地域のコンテンポラリーと比較して見る価値があります。
コンテンポラリーダンスの代表例
日本でもなじみのある以下の作品・事例が挙げられます。
- Sia「アライヴ feat. 土屋太鳳 / Alive feat. Tao Tsuchiya」
- 米津玄師「Loser」
- 森山未來「CeBIT」
- 欅坂46「不協和音」
いずれも知名度の高いアーティスト・作品で、身近に感じやすいはずです。
Sia「アライヴ feat. 土屋太鳳」
ダンスに定評のある女優・土屋太鳳さんが、Siaの楽曲「アライヴ」に合わせてコンテンポラリーを披露。演技力と身体能力が相まって、日本でも話題になりました。
米津玄師「Loser」
若い世代に人気の米津玄師さんの「Loser」でもコンテンポラリーの要素が見られます。ジャンル分けを超える独自の雰囲気が、楽曲世界へ観る者を引き込みます。
森山未來「CeBIT」
東京2020オリンピックでも注目された森山未來さんが、予測不能なムーブメントを展開。多様なダンス経験に裏打ちされた表現力が光ります。
欅坂46「不協和音」
人気アイドルグループ欅坂46の同曲にもコンテンポラリーが取り入れられています。タイトル通り“不協和”を身体で示し、センターの平手友梨奈さんだけ振付が異なる構成が特徴です。
まとめ
「最先端のダンス」とも呼ばれるコンテンポラリーには世界共通の明確な定義がなく、各国の文化や音楽の影響で常に新しく定義し直されていきます。固定の基準がないからこそ今も変化を続け、表面上は抽象的でも、奥には深いテーマが潜んでいることを知れば見方が変わるはずです。
面白さの核心は、現実のテーマや歴史的背景を“感じ取れる”ところにあります。専門知識がなくても、人は感じる力を持っています。その感受が、コンテンポラリーを成立させる大切な要素です。
日本でも著名人がコンテンポラリーを踊る機会が増えています。好きな曲や作品のテーマを、この機会に深掘りしてみてはいかがでしょうか。
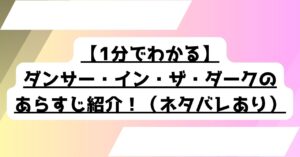
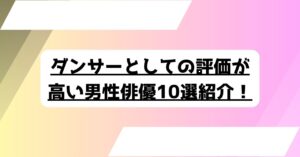
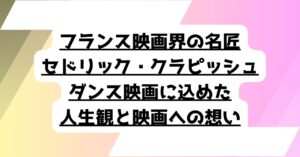
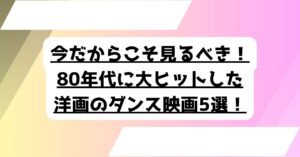
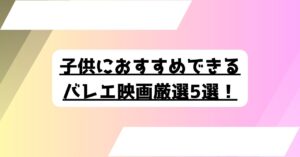
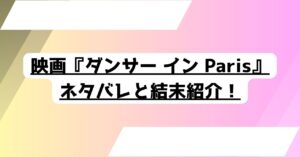
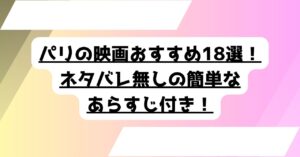
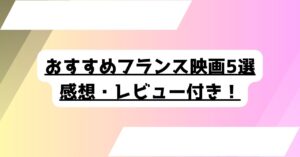
コメント