セドリック・クラピッシュはフランスを代表する映画監督の一人です。
1996年の『猫が行方不明』でベルリン国際映画祭の批評家協会賞を受賞して注目されて以来、『スパニッシュ・アパートメント』(2002)や『PARIS パリ』(2008)など、パリの日常や若者たちの群像をウイットに富んだ軽妙なタッチで描き続け、観る者を魅了してきました。
そんなクラピッシュ監督が長年温めてきた夢を叶え、敬愛するダンスを題材に完成させた作品が『ダンサー イン Paris』です。
この記事ではクラピッシュ監督の経歴や創作スタイル、影響を受けたもの、そして『ダンサー イン Paris』の背景と制作意図をひも解きながら、彼の人生観と映画観に迫ります。
セドリック・クラピッシュの経歴
クラピッシュ監督は1961年、パリ近郊のヌイィ=シュル=セーヌに生まれました。
大学で映画制作を学んだ後、ニューヨーク大学でも2年間研鑽を積み、1980年代に幾つかの短編映画を監督します
1992年に長編デビュー作『百貨店大百科』を発表し、続く1996年の長編3作目『猫が行方不明』がベルリン国際映画祭で高い評価を受けると一躍脚光を浴びました。
以降、『家族の気分』(1996)や『パリの確率』(1999)、『PARIS パリ』(2008)といったパリを舞台に人々の人生模様を描く作品を次々と発表すると同時に、『スパニッシュ・アパートメント』(2002)、『ロシアン・ドールズ』(2005)、『ニューヨークの巴里夫(パリジャン)』(2013)の青春三部作で若者たちの成長と葛藤をユーモアたっぷりに描き出し、フランス映画界のヒットメーカーとしての地位を確立しました。
近年も『おかえり、ブルゴーニュへ』(2017)やパリを舞台にしたラブストーリー『パリのどこかで、あなたと』(2019)など話題作を生み出し続けています。
長編以外でも、自身が熱心なバレエ&ダンス愛好家であることから、パリ・オペラ座のエトワール(最高位ダンサー)に迫ったドキュメンタリー『オーレリ・デュポン 輝ける一瞬に』(2010)やオペラ座バレエ公演の映像作品なども手掛けており、その活動の幅は多岐にわたります。
なお、監督自身が自作映画にカメオ出演する遊び心も持ち主で、ファンにとっては作品中に彼の姿を探し出すのも楽しみの一つとなっています。
創作スタイル
クラピッシュ作品の特徴としてまず挙げられるのは、日常生活をユーモアと人間味豊かに描く巧みさです。
実際、彼は作品を通じてウイットに富んだ軽妙な人生模様を映し出し、観客を惹きつけてきたと言われます。
パリの街角に生きる様々な人々の群像劇や、若者たちの青春模様を温かい視点で描くことが多く、登場人物同士の機知に富んだ会話やちょっとしたハプニングのユーモアが作品全体に爽やかな印象を与えています。
また、若い世代のエネルギーをフィルムに収めることもクラピッシュ監督の大きな動機だといいます。彼は「20代の若者たちは情熱が身体からほとばしっている。その眩しさを映画にしたい」と語っており、
実際デビュー間もない新人俳優を積極的に起用していました。
一方で近年のクラピッシュ監督は、フィクションとドキュメンタリーの融合にも取り組んでいます。
例えば『おかえり、ブルゴーニュへ』(2017)ではワイン農園でのブドウ収穫シーンをドキュメンタリータッチで撮影しつつ、物語部分は従来の劇映画の手法で演出することで、一つの作品の中に現実と虚構を巧みに織り交ぜました。
このアプローチは最新作『ダンサー イン Paris』でも活かされており、特にダンスカンパニーの稽古風景などは演出を加えずドキュメンタリー的手法でカメラに収め、後の編集で物語に組み込んでいます。
こうした実験的な撮影手法によって、物語のリアリティと躍動感をいっそう高めているのです。
また監督自身、「直感に頼る部分と緻密に計算して構築する部分の両方を持ち合わせている」と述べており、感覚的なひらめきを大事にしつつも綿密なリサーチを行って作品を作り上げるバランス感覚が、その独自のスタイルを支えています。
実際『ダンサー イン Paris』の編集では、往年の名作ミュージカル映画を数本調査し、
歌やダンスシーンが全体の何%を占めるか分析した上でダンス場面の尺を調整したというエピソードもあります。
エンターテインメントとしての心地よいリズムを保ちながら、ダンスそのものの魅力もしっかり伝える工夫が感じられますよね。
影響を受けたもの
クラピッシュ監督の創作の背景には、多様な文化や芸術から受けた影響が見られます。
中でも大きいのがダンスとの出会いでした。
本人によれば14~15歳の頃、パリ市立劇場の会員パスを使って毎週のようにコンテンポラリーダンス公演を観に通い、
そこでカロリン・カールソンやピナ・バウシュといった1970~80年代に活躍するダンサーたちの舞台に魅了されたといいます。
この体験がきっかけでダンスへの愛情が芽生え、自ら踊り手になろうとまでは思わなかったものの(「パーティで踊る程度で十分」と笑っています)、
観客として踊りの芸術に深い敬意を抱くようになりました。
こうしたダンスへの憧れは年月を経ても強まり続け、映像作家としてバレエやコンテンポラリーダンスに関わる仕事を積極的に手掛けてきた原動力になっています。
映画監督としてのクラピッシュに影響を与えたものとしては、多彩なジャンルの作品や芸術観も挙げられます。
彼は往年のミュージカル映画が持つダンスシーンにも関心を寄せていますが、
それらの多くは「あくまでフィクションの物語を語るためにダンスを用いているのであって、
ダンスそのものを真正面から扱った映画はそれほど多くない」というのが彼の見解。
実際、ダーレン・アロノフスキー監督の『ブラック・スワン』(2010)については「あれは自分にとってダンス映画の悪い例だね(笑)」と語っており、過去の作品に安易に倣うのではなく独自のアプローチでダンス映画に挑みたいという強い意志がうかがえます。
また、クラピッシュ監督はフランスの作家アルベール・カミュの「生きている限り表現し続けたい」という言葉に共感し、日本の黒澤明監督が多彩なジャンルで人生の様々な側面を描いたことを心から尊敬しているんだとか。
自らも「人生を表現するために映画を撮っている気がする」と語るその姿勢には、
文学や映画界の偉大な先人たちから受け取った創作哲学が色濃く反映されていると言えるでしょう。
『ダンサー イン Paris』の背景と制作意図
クラピッシュ監督にとって『ダンサー イン Paris』(原題:En Corps)は、20年越しの夢が実を結んだ特別な作品です。
彼は約20年間も「いつかフィクションで本格的なダンス映画を作りたい」と温め続けてきたアイデアを、ついに最新作で現実のものとしました。
長年ダンスを愛し、その世界を深く知る彼ならではの視点で、「これまでの映画で描かれたことのないダンサーのドラマを撮りたかった」のだと言います。
物語はパリ・オペラ座のバレエダンサーである主人公エリーズが怪我によりバレリーナの夢を絶たれかけ、新たにコンテンポラリーダンスの世界で再生していく過程を描いています。
クラピッシュ監督はこのストーリーに自身のメッセージを託しました。それはクラシックとコンテンポラリーという異なるダンスの融合です。
彼は「伝統を生かしながら前衛的な革新を取り入れることで芸術は豊かになる」と信じており、
劇中でもクラシックバレエと現代的なダンスを対比させつつ両者の調和に希望を見出しています。
実際、物語はクラシックバレエで幕を開けてコンテンポラリーダンスで終わりを迎え、音楽もクラシック曲と現代音楽が入れ替わりながら流れていきます。
伝統と革新の両方に敬意を払い、「どちらが優れているということではなく、融合こそが新たな芸術を生む」という思いがラストシーンにも込められているのです。
『ダンサー イン Paris』の制作にあたって、クラピッシュ監督は徹底したリアリティの追求にもこだわりました。
主役のエリーズ役には「踊れる女優」を求め、実際にパリ・オペラ座バレエ団で活躍する現役トップダンサーのマリオン・バルボーを大抜擢しています。
彼女自身がエトワール(最高位)目前の実力者であり、クラシックもコンテンポラリーも踊りこなす次世代スターであったことが起用の決め手となりました。
また、劇中でコンテンポラリーダンスのカンパニーを率いる振付家役には、世界的に著名な振付家ホフェッシュ・シェクター本人を起用し、振付・音楽も彼に担当してもらうという贅沢な試みを行っています。
スタントや代役ではなく本物のダンサーたちが放つ躍動感をそのまま映像に収めることで、観客にもダンスの迫力と喜びがダイレクトに伝わる作品に仕上げているのです。
さらに本作には、クラピッシュ監督ならではのユーモアが随所に散りばめられている点も見逃せません。
重厚なバレエの世界を舞台にしながらも、小気味よい会話劇や登場人物たちの人間味あふれるエピソードが物語に軽やかさを与えており、「クラピッシュ作品らしいウイットに富んだシーンが多数盛り込まれていて飽きさせない」と評されています。
シリアスなテーマの中にも観客をクスリとさせる笑いを忘れないのは、監督がこれまで培ってきた持ち味といえるでしょう。
制作の背景としては、新型コロナウイルスのパンデミックも本作に大きな影響を与えました。
2020~21年当時、パリ・オペラ座を含む劇場が封鎖されダンサーたちが舞台で踊れない状況が続く中で、クラピッシュ監督は「ダンスは永遠だ」というエールを込めて本作の製作を決意したといいます。
劇中でエリーズが突然踊る場を失い将来を絶たれそうになる展開は、まさにコロナ禍で先行きの見えない不安を抱えた私たち自身の姿と重なり、より強いリアリティをもたらしていると言えるでしょう。
監督自身、「あの危機を乗り越えれば止まってしまったかに見えた人生もまた動き出すんだ」というメッセージを本作に込めたと語っており、
困難を経ても前に進む力を描く物語はコロナ後の世界に生きる観客への励ましともなっています。
実際、監督はロックダウン中にオペラ座のダンサー達が自宅で練習する様子を撮影した動画を集め、
4分間の短編映像『Dire merci(メルシーと言うこと)』に編集してYouTubeで発表するといった活動も行いました。
その映像を通じて、多くの人々がダンスによる「解放」の感覚を共有できたといい、この経験が『ダンサー イン Paris』の着想をさらに後押ししたようです。
近年の映画への姿勢
デビューから30年以上が経過した現在も、クラピッシュ監督は旺盛な創作意欲を失うことなく精力的に活動しています。
近年はデジタル配信の分野にも進出し、自身の青春三部作に続く物語として現代の若者を描いたTVシリーズ「ギリシャ・サラダ」(2023年、Amazonプライム配信)を手がけるなど、新しい形態にも挑戦を続けています。監
督本人は「青春映画というジャンルにこだわっているわけではない」としながらも、「どうしてもデビューしたばかりの若い俳優たちに惹かれてしまう」と語っており、常に次の世代のエネルギーを作品に取り込む姿勢は変わりません。
実際『ダンサー イン Paris』にも20代の新人ダンサーを主演に起用し、その眩い才能をスクリーンに焼き付けましたが、そうした若い才能とのコラボレーションこそが自身の映画作りの大きな原動力だと述べています。
またクラピッシュ監督は、一つのジャンルやスタイルに安住せず常に新たな発見を求める姿勢を持っています。
ダンス映画に初めて挑戦したことで多くの学びと気づきがあったといい、
「次は是非フィクションのミュージカル映画にも挑戦してみたい」と新たな野望を語っています。
ドキュメンタリー、シリーズドラマ、ダンス映画と活躍の場を広げる中でも一貫しているのは、「なぜ映画を撮るのか」という問いに対する彼の明確な信念でしょう。
クラピッシュ監督は「生きている限り、人生を表現するために映画を撮り続けたい」という思いを持っており、その姿勢は自ら敬愛する黒澤明監督にならい様々なジャンルで人生の多面性を描こうとする姿にも表れています。
どんな題材であれ根底にあるのは人間への洞察と人生への深い眼差しであり、そこにユーモアと希望を織り交ぜながら物語を紡ぐのがクラピッシュ流の映画哲学だと言えます。
『ダンサー イン Paris』においても、彼はダンスという芸術を通じて「人生は困難を経ても再び輝き始める」という普遍的なテーマを描き出しました。
今後もクラピッシュ監督はその瑞々しい感性と探究心をもって新たな物語に挑戦し続け、私たち観客に人生の喜びと発見を届けてくれることでしょう。
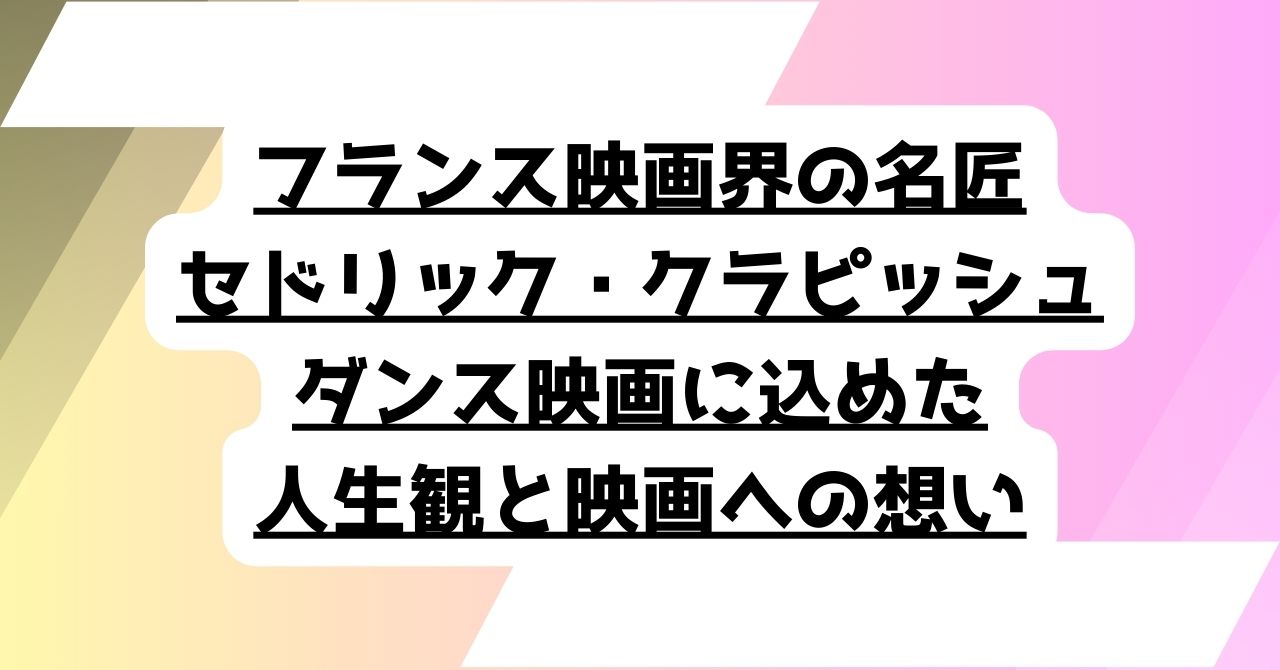
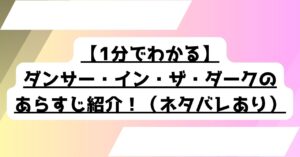
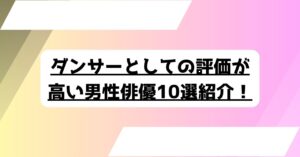
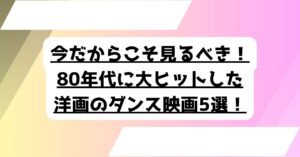

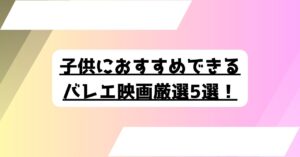
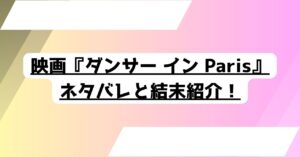
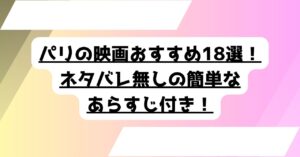
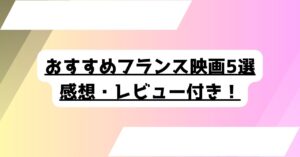
コメント